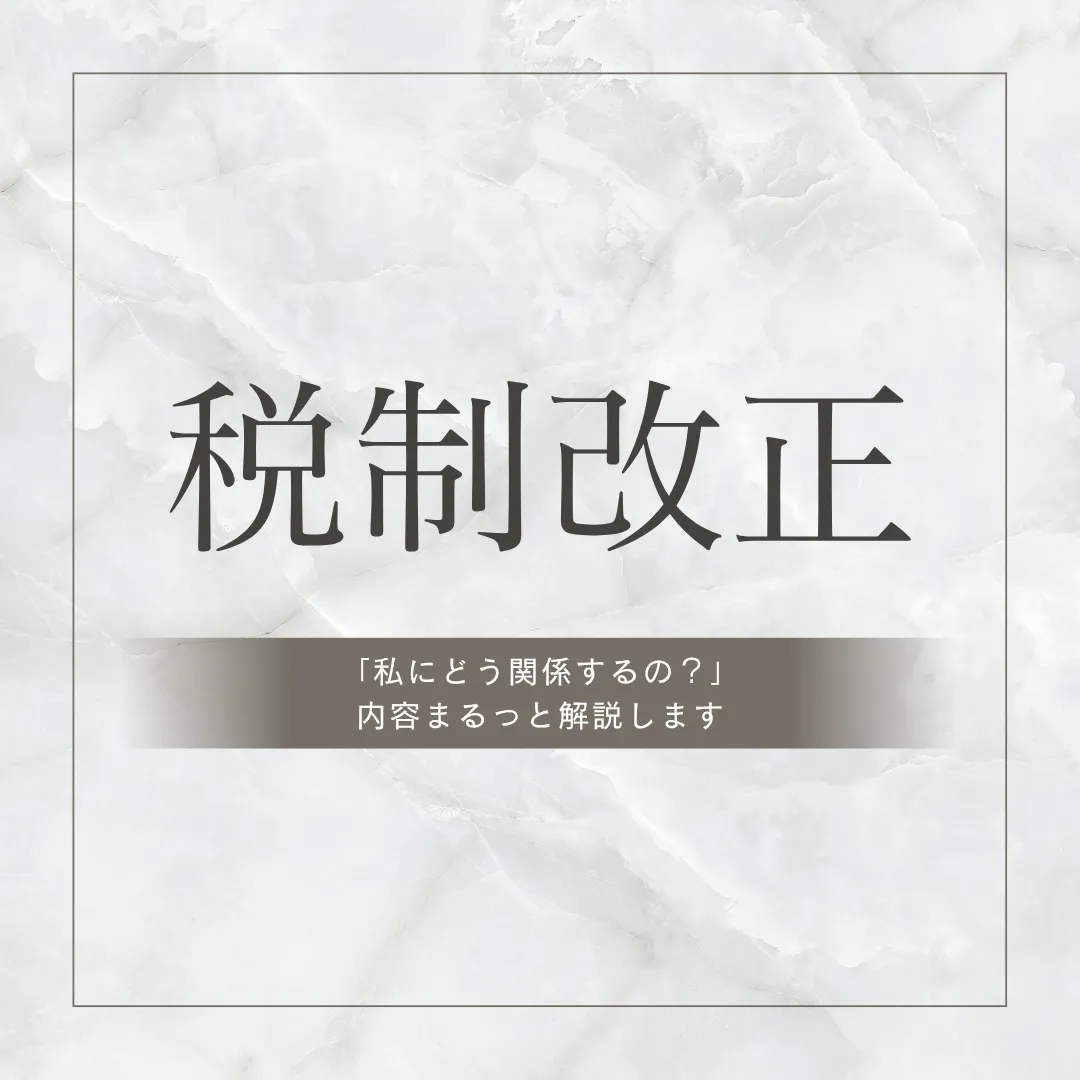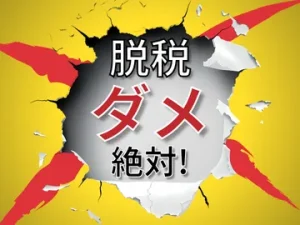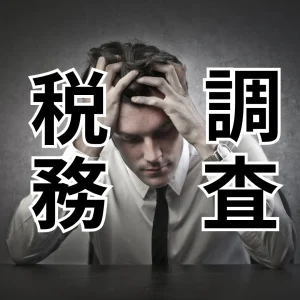Web制作や開発の現場では、「業務委託+副業+フルリモート」など、多様な働き方が当たり前になってきました。
そんな時代に、「年収の壁って関係あるの?」と思いがちですが、実はIT業界こそ影響を強く受ける制度変更が2025年から始まっています。
とくに「103万円までに収めておけばOK」という認識は、すでに時代遅れです。
このコラムでは、IT業界に特有の働き方と2025年以降の税制変更をふまえ、損しない働き方・人材マネジメントの視点をやさしく解説します。
目次
1. 「年収の壁」が変わると何が起きる?
2025年から、所得税と住民税に関わる「非課税ライン」が引き上げられました。
これまで「103万円の壁」で年収を抑えていた学生や主婦、業務委託者などが、より柔軟に働けるようになったのが最大のポイントです。
| 年収の壁 | 改正前 | 改正後(2025年~) |
| 所得税の非課税ライン | 約103万円 | 約160万円 |
| 住民税の課税開始ライン | 約100万円 | 約110万円 |
| 親の扶養控除(特定親族) | ~103万円 | ~150万円(最大63万円控除)、188万円超で消失 |
2. Web・IT業界の“あるある”はここに注意!
ケース1:給与+副業(業務委託)
IT業界では、正社員として働きつつ副業で業務委託を受けるなど、いわゆる“ハイブリッド型”の働き方が一般化しています。
たとえば「正社員で月25万円、副業で月5万円」の人は、年間収入が360万円。副収入が年20万円を超えているため、確定申告が必須になります。さらに本業と副業の合計が160万円を超えていれば、所得税の課税対象にもなります。
住民税の申告漏れや、会社に副業が“バレる”ケースもこのパターンで多発しています。
ケース2:業務委託メンバーの「収入制限」
業務委託で稼働する人が「扶養内でいたいので103万円以内に収めたい」と希望するケースも多く見られますが、2025年以降はその制限が大きく緩和されました。
年収160万円までなら基本的に所得税は発生せず、従来よりも業務アサインの幅を広げやすくなるのです。
この制度変更は、「控えめに働きたい人」を無理に増やす必要も、「稼ぎたい人」を止める理由もなくなったことを意味します。
組織にとっては、稼働率を最大化しやすくなる絶好の機会といえます。
3. 経営者が見落としがちな“年収の壁”リスク
制度が変わっても、その内容を正しく伝えられなければ、組織には逆にリスクが増える可能性もあります。
特に以下のような点には注意が必要です。
- 「扶養を外れるから契約を切りたい」申し出
→ 税制に対する誤解や不安から、従業員・業務委託者が自ら稼働を減らしたり離脱したりすることを選ぶ。
→ 特に家族の控除を気にする人に多く、事前の正しい情報提供が予防策に。 - 住民税通知による“副業バレ”トラブル
→ 副業収入を確定申告せず、住民税の課税通知が本業側に届き発覚。
→ 従業員の信用問題や社内関係の悪化につながるケースも。
→ 普通徴収の選択や副業のガイドライン整備が重要。 - 社内理解のばらつきによる納得感の格差
→ 同じような働き方をしていても、「自分は申告して税金が増えたのに、あの人は…」といった不公平感が生まれる。
→ 明文化された制度説明や説明会の実施で、透明性と納得感を強化。 - 経理・人事側の知識不足による実務ミス
→ 住民税の徴収方法の誤り、年末調整での副業収入の見落としなど。
→ 制度変更に対応したマニュアル更新と社内研修がカギ。
こうした問題は、あらかじめ制度を正しく共有するだけで防げるものが多いため、社内研修や人事マニュアルへの反映が有効です。
4. 「個人の最適化」と「チーム最適化」をどう両立するか?
これからの人材活用において、「控除を気にして仕事を減らす」という判断は、会社側・本人双方にとって損失です。
たとえば、従業員の年収見込みを年末に通知し、「このままなら扶養内に収まりますよ」といったフィードバックを行えば、本人も安心して稼働できます。
また、業務委託においても「この稼働ペースだと年間160万円を超えます」と先に提示することで、余計な不安やトラブルを未然に防ぐことが可能です。
さらに、社内教育に「税金や控除の仕組み」を組み込み、税制に強いチームを作ることは、将来的なフリーランスや経営人材育成にもつながります。
税金の知識を「個人任せ」にせず、会社としても一歩踏み込むことで、制度に振り回されない強いチーム作りが実現します。
5. まとめ:「知らずに損する人を減らす」のが強い組織
税制は、知っていれば味方になり、知らなければ足かせになるものです。
とくにWeb・IT業界のように、自由度の高い働き方が広がる分野では、税金や保険の制度を正しく理解し、個人と組織の両方にとって最適なバランスを設計できることが競争力に直結します。
「とにかく抑えておこう」「余計なことを考えたくない」から卒業し、
「制度を知って、働き方を最適化する」ことがこれからの標準です。