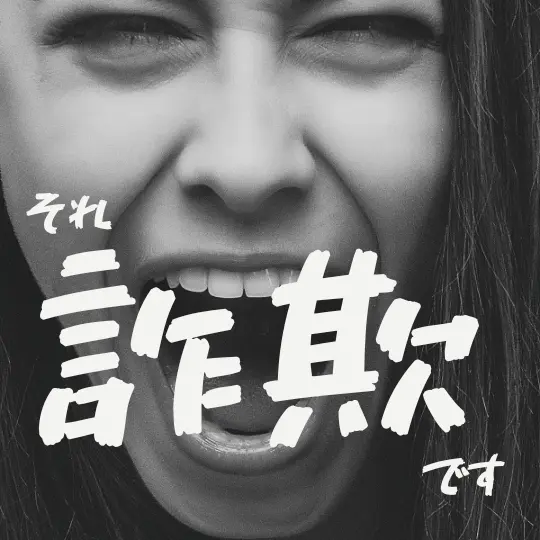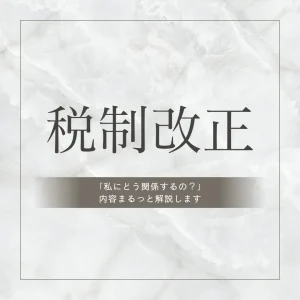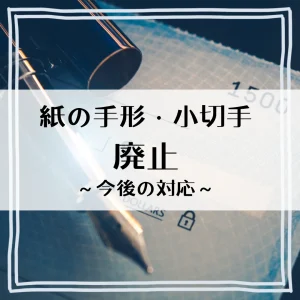目次
確定申告は税理士へ!架空の事業所得で損失を作るリスクとは?
確定申告の時期になると、「お金のプロ」を名乗る人々がSNSでさまざまな節税方法を語っています。その中には、法律に違反する手法も含まれており、最近では架空の事業所得を作り、意図的に赤字を計上することで税金を減らす手口が話題になっています。しかし、これは明確な脱税行為であり、絶対に行ってはいけません。
今回のニュースの概要
東京国税局は2024年2月13日、経営コンサルティング会社を経営する東京都渋谷区の菊池志門役員(48)を所得税法違反などの疑いで東京地方検察庁に告発しました。
関係者によると、菊池役員は税理士資格がないにもかかわらず、確定申告の際に知人の税務書類作成を請け負い、会社員の男女5人に対して架空の副業で損失を計上する手口を指南。これにより、2023年までの4年間で約1億2000万円の所得を隠し、およそ2000万円の所得税を免れたとされています。
また、菊池役員は無資格で税理士業務を行ったとして、税理士法違反の疑いでも告発されており、5人から報酬として約700万円を受け取っていたとみられます。
確定申告の代理は税理士のみが許されている
まず、確定申告を税理士以外の第三者に依頼することは法律違反。税理士法では、税務相談や申告書の作成代行は原則として税理士のみが行える業務と定められています。にもかかわらず、一部の無資格者が「確定申告サポート」などと称して業務を行い、不適切な節税策を指南するケースが後を絶ちません。
今回のニュースでも、会社役員が会社員の確定申告を支援すると称し、架空の事業所得を計上して損失を作る方法で約2000万円の所得税を免れたとして告発されています。このような行為は、関与した納税者自身も責任を問われる可能性があります。
税務署はどのようにして不正を見抜くのか?
「架空の事業所得で損失を作れば税金が減らせる」と考える人もいるかもしれませんが、税務署はこうした不正を見逃しません。以下のような方法で不正申告を発見します。
- 事業実態の確認
事業を行っているかどうかは、開業届や事業用口座の動き、売上の有無などを調査すれば簡単に判明します。実際の取引がないにもかかわらず経費だけを計上している場合、すぐに疑われます。 - 過去の申告との比較
突然、前年までなかった事業所得が発生し、大きな損失を計上している場合、税務署はその背景を精査します。特に、給与所得との損益通算を目的とした赤字申告は要注意です。赤字を何年も続けるって単純にやらない方が儲かるということ…。怪しいと感じるのはごく当たり前のことです。 - 第三者からの情報提供
SNS上で違法な節税スキームを宣伝していると、第三者からの通報が寄せられることがあります。また、税務署はインターネット上の情報を収集し、不審な事案を特定することもあります。 - 税務調査の実施
税務署が不審に思えば、調査が行われます。事業の実態を証明する書類や取引記録がない場合、申告内容の整合性が取れないことが発覚し、不正が露呈します。 - 税務調査は4~5年目に入ることが多い
税務署は不正が疑われるケースについて、すぐに調査を行うとは限りません。多くの場合、数年分のデータを蓄積し、不審な点が積み重なったタイミング、特に4~5年目あたりに税務調査が入ることが多いのです。そのため、一度成功したと思っても、後々発覚するリスクが高いことを理解しておくべきです。
悪さをした場合は5年間、ハラハラドキドキし続けます。
今回のペナルティはどうなる?
今回のように、違法な申告が発覚すると、本来支払うべき税金に加え、延滞税や過少申告加算税が課されます。
- 延滞税
本来の納税期限までに納付されなかった場合に発生する税金で、未納期間に応じた利息が加算されます。ざっくり言うと最初の2ヶ月は2.4%。それ以降は8.7% - 過少申告加算税
本来の税額よりも過少に申告していた場合に課される税金で、通常は10%(50万円を超える部分は15%)が加算されます。
このようなペナルティを回避するためにも、確定申告は適正に行うことが重要です。
まとめ:正しい申告を税理士と共に
確定申告は、適切なルールのもとで行う必要があります。不適切な節税策に手を出すと、後々大きなペナルティを受けるリスクが伴います。特に、税務調査が入れば、追徴課税だけでなく、悪質な場合は刑事告発されることもあります。
税金の正しい知識を持ち、信頼できる税理士に相談することが、最も安全かつ適切な節税対策です。確定申告のことでお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。